

【第2回】
山に入ってしばらくするまで、すべては順調であった。
若者は夜の木立のざわめきやどこか遠くで聞こえる獣の鳴き声を
薄気味悪く思いながらも、うまく抜け出せた事に安堵していた。
しかし程なく、下の方に灯りが現れた。木々の影に見え隠れして
ちらちらと揺れている。
若者は背筋を凍らせた。あれは追手ではあるまいか。
しかも、次第に数が増えるようである。
揺れながら、だんだんに灯りは大きくなって迫ってくる。
若者は我を忘れて走り出した。
方向も何も考えずただひたすらに走った。
途中で何度か転んだようであるが、よくわからなかった。
気がつくと、あたりに濃い霧が漂っていた。
若者は立ち止まった。
見渡してみても、もう追っ手の灯りはどこにも見えない。
そればかりか、周囲はまったく静まり返っていて木ずれの音すらも
しなかった。
ここはどのあたりなのだろう。若者は足元を確かめながら霧の中を
歩き出した。
どことも知れずにしばらく歩き続けると、静寂の中にかすかに
何かの音を耳が拾うようになった。
あてをつけて目指してゆくと、次第に大きくはっきりと聞こえてくる。
水音のようである。
さらに進むとそのうちに、水のにおいが漂い、空気がひんやりと
するようになった。
そして何度目かに枝を掻き分けると、急に空間が開けて、
川べりに若者は立っているのだった。
浅い川で、水はさらさらと流れている。たいそう澄んでいることが
夜と霧の中でも知られる。
ふと、視界が何か動くものを捕らえたような気がして見やると、
少し離れたところの対岸に人が一人いた。
水を汲んでいるようである。
今更見を隠すこともできず、息を飲んで身じろぎもせずにいると、
気がついてこちらを見返してきた。
じっと見つめた後、迷われたのですか、と尋ねてきた。
女の声だった。
その言葉は普段聞きなれているのとは違った調子をしていたし、
女は見たこともない衣を纏っているのが遠目にも分かったので、
自分の国の人間ではないだろうと思った。
それでも警戒を解ききらずに黙ってうなずくと、女は、
よければ付いて来なさい、この辺りの地形はたいそう複雑です、
と言って背を向けた。
去っていこうとするのを見て、若者は一瞬躊躇したが、このまま
さ迷っているわけにもいかないのでついてゆくことにした。
岩や倒木を踏んでゆくと、川は容易に渡ることができた。
【続く】
『雑記』
作:岸本 余白
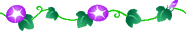
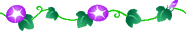
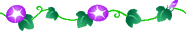
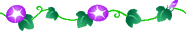
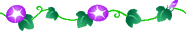



![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
