【第1回】
むかしむかし、あるところに、おじいさんとおばあさんが
いない国があった。
年を取った人間は、いつの間にかいなくなってしまうのであった。
彼らはそれまでまじめに勤めてきた報酬として、どこか美しい
穏やかな場所へ行くことができ、そこで作物の出来不出来や、
嫁姑のいさかいなどにわずらわされることなくのんびりと余生を
すごすのだと一般には言われていた。
その国の人間の五分の四はこれを信じ、残りの五分の一は
ひそかに疑っていた。
老人、といっても個人差があって年齢でくくることは難しいので、
この国では慣習として、歯の数が基準にされていた。
残った歯の数が二十を切ると、老人と見なされるのであった。
この国に、不幸にも病でほとんどの歯を失った若者がいた。
若者は残りの五分の一の一人だった。
若者はおびえた。
自分の歯が二十を下回っていることが知れたらどうなるのだろう。
どこかにつれて行かれるのか、あるいは殺されてしまうのだろうか。
さいわい、若者は手先が器用だったので、手製の入れ歯を作って
誤魔化していた。
両親は早くに亡くなっており、一人住まいであるので、当面のところは
なんとかなりそうである。しかし、そう長々と隠し通せるものではない、
そのうち必ずばれてしまうにちがいないと思い、日々を恐怖と不安の中で
過ごしていた。
耐え切れなくなって、若者はとうとう逃げ出す決心をした。
いつものように仕事をした後、こっそり家を抜け出して
夜闇にまぎれて山中を歩き、なんとか国ざかいを越えて
隣国に入ろうという計画であった。
幼い頃から、山には恐ろしい化け物がいると聞かされていた。
今まで一人で、しかも日が暮れてから入ったことはなかった。
恐ろしくはあったが、それでも死ぬよりはましだと思った。
人が入りづらいということはかえって逃げるのには好都合でもあった。
【続く】
『雑記』
作:岸本 余白
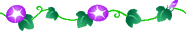
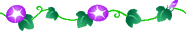
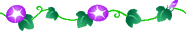
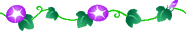



![]()
![]()
![]()
![]()
